![]()
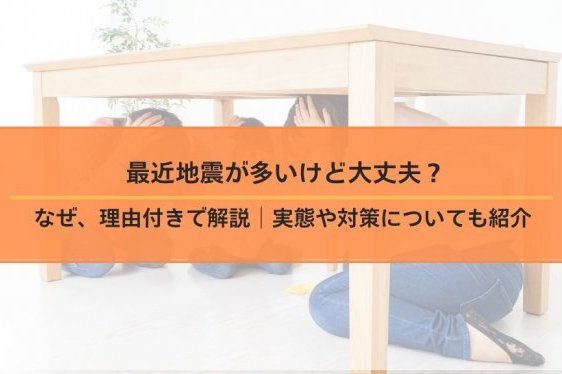
「最近、地震が多いけど、大丈夫?」 このように不安を抱く方は多いのではないでしょうか。 地震が発生すればテレビで速報が流れ、またSNSでの拡散によって地震を身近に感じやすい時代ではあります。 しかし、本当に地震は増えているのでしょうか。 本記事では、データを元にした実態やリスクを整理し、安心につながる具体的な対策も解説します。 実態を把握した上で、地震の揺れや二次災害に備えた対策を取り、不安を少しずつ「安心」に変えていきましょう。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 「最近地震が多い」感じるのはどうして? 「最近地震が多い」と感じる背景には、情報環境の変化が関わっています。 たとえば、気象庁が緊急地震速報を出した回数は、東日本大震災以降増えています。 このほか、SNSでも「揺れた」といった投稿が拡散しやすいことなど、地震について意識する機会が増えていることも挙げられます。 ▶関連コラム:日本で地震が多い県ランキング│地震が多い県で安心して暮らす7つの対策もご紹介 「地震が最近多い」は本当?データを確認 では、一方で本当に地震の発生回数は増えているのでしょうか。 気象庁の震度データベースから、直近10年と、10~20年前、20~30年前の地震で、震度5弱以上の揺れ(気象庁が定める、木造建物に影響を与え始めるとされる震度)を対象に集計を取りました。 直近10年(2015年9月~2025年9月):141地震 10~20年前(2005年9月~2015年9月):148地震 20~30年前(1995年9月~2005年9月):130地震 ▶参考:気象庁 震度データベース検索 その結果、10年単位で確認すると、特に地震の発生回数が増えているとはいえない結果が確認できました。 なお、直近10年の場合は熊本地震や能登半島地震、10~20年前は東日本大震災の影響があり、地域ごとに地震の発生回数に偏りがある点は認識が必要です。 地震発生時のリスクを確認 地震は揺れそのものに加えて、津波や火災、液状化といった二次災害や住宅被害による経済的負担を伴います。 特に首都直下地震や南海トラフ地震など巨大地震のリスクは常に意識しておく必要があります。 首都直下地震、南海トラフ地震などによる揺れ ▶参考:内閣府 想定される大規模地震 首都直下地震はマグニチュード7クラスの発生が想定され、東京23区で震度6強以上の揺れが広範囲に及ぶ可能性があります。 南海トラフ地震はさらに規模が大きく、東海から四国、九州にかけて震度7クラスの揺れが想定されています。 いつ地震が発生するのか予測も困難ですので、揺れに対する対策を早期に進める必要があります。 ▶関連コラム:南海トラフ地震が起こるとどこが危ないのか|県やエリア・対策も解説 津波、火災、液状化といった二次災害 大地震の後には揺れ以外の被害も想定されます。 沿岸部では津波による浸水や流出被害が懸念され、都市部では同時多発的な火災が広がるリスクがあります。 さらに、埋立地や軟弱地盤では液状化により住宅や道路が沈下、傾斜し、生活基盤を損なう可能性があります。 住宅の再建、修復などによる経済的な影響 住宅が大きな損傷を受ければ、修繕や建て替えに多額の費用がかかります。 地震保険や自治体の補助金で一部はカバーできますが、全額をまかなえるわけではなく、自己負担は大きくなりがちです。 ローン返済中に被災すると二重ローンになるケースもあり、事前の経済的備えが欠かせません。 ▶大地震でも「無傷」、負債を防ぐ「百年住宅」の家 「地震が多くても大丈夫」安心を得るための対策 地震への不安を軽減するには、建物の構造や日常生活での備えを整えることが大切です。 耐震基準を満たした家づくりから家具の固定、地域リスクへの理解まで、多面的な対策で「大丈夫」と感じられる安心を得られます。 耐震基準や等級、揺れに強い家にする 家具や家電の転倒防止対策を取る 耐久性が高い建材を利用する 津波や洪水の発生に耐えられる仕様にする 火災の発生時に延焼しづらい仕様にする ハザードマップの確認など日常的な工夫を加える 耐震基準や等級、揺れに強い家にする 現行の建築基準法を満たした住宅は震度6強〜7の揺れにも倒壊しない耐震性能を備えています。 加えて安心を求めるなら、耐震等級2や3といった上位等級を検討しましょう。 ▶大地震でも安心「無傷の住まい」が分かるカタログ4点セットはコチラ 耐震等級など定量的な指標に加えて、地震の揺れに強く耐火性・耐久性にも優れた、鉄筋コンクリート造(RC造)を選ぶことで、都市部や沿岸部など災害リスクの高い地域での長期的な安心につながります。 ▶関連コラム:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介 家具や家電の転倒防止対策を取る ▶内閣府 誰にでもすぐできる家具転倒防止対策 室内の安全を確保するには、家具や家電の転倒・落下を防ぐ工夫が欠かせません。 L字金具で壁に固定したり、滑り止めシートや突っ張り棒を設置することで揺れによる転倒リスクを減らせます。 特に冷蔵庫や本棚など重量のある家具は、転倒時に大けがにつながりますので、日常的な点検と対策が重要です。 耐久性が高い建材を利用する ▶耐震性の高い鉄筋コンクリート製の「壁式構造」 住宅そのものの耐久性を高めるには、劣化や火災、浸水に強い建材を選ぶことが有効です。 鉄筋コンクリート造など、長期的な耐久性を期待でき、揺れによる影響を受けづらい建材を採用することで、災害時の損傷を抑えやすくなります。 定期的なメンテナンスも合わせて行うことで、長期にわたり安心できる住まいを維持できます。 津波や洪水の発生に耐えられる仕様にする ▶RC造の屋上に設けるタイプの津波シェルターペントハウス 沿岸部や河川沿いに住む場合は、水害リスクを考慮した仕様が不可欠です。 基礎を高くする「高基礎」や盛土、1階をピロティにする設計や緊急時に避難できる間取りなどで浸水による人的・物的被害を軽減できます。 また、コンクリート構造は木造よりも津波や洪水による流出に強く、被災後のカビや腐敗を防ぎやすい点も特徴です。 立地条件に合わせて、建材や建築計画も工夫しましょう。 ▶関連コラム:南海トラフ地震発生時どこに逃げる?避難行動の想定や事前の対策も紹介 火災の発生時に延焼しづらい仕様にする ▶構造材自体が耐火性を持つ百年住宅の家 地震後の火災に備えるには、不燃材や準不燃材を活用した外壁や屋根を採用することが有効です。 コンクリートなど耐火性の高い建材を選べば、延焼を防ぐことができ、避難の時間を確保できます。 特に防火地域・準防火地域では法的に耐火性能が求められますので、規制に適合した設計と素材選びが義務付けられています。 木造や鉄骨造で耐火性能を高める場合は建築コストが増加しますので、これらの地域では鉄筋コンクリート造での建築が推奨されます。 ハザードマップの確認など日常的な工夫を加える ▶静岡市 洪水ハザードマップ 安全な暮らしの第一歩は、地域の災害リスクを正しく知ることです。 自治体が公開するハザードマップを確認すれば、浸水・液状化・土砂災害などの危険箇所を把握できます。 避難経路や避難所を家族で共有しておくことも重要です。 日常的に防災への備えを家族間で共有し備蓄を整えることで、不安を安心へと変えましょう。 地震が多いとき、よくある質問【Q&A】 「地震が多いけど大丈夫?」という不安は誰もが抱くものです。 記事の終わりに、寄せられることの多い質問に答え、正しい知識と行動で安心につなげるヒントをご紹介します。 Q:小さな地震が多い場合、大地震の前兆ですか? A:小さな地震が続くと「大きな地震の前触れでは?」と心配になりますが、必ずしもそうではありません。 群発地震や余震は自然な活動で、大地震に直結するとは言い切れません。 ただし、過去には大地震の前に余震が観測された例もありますので油断は禁物です。 気象庁や地方自治体などの信頼できる公的機関の情報を元に、冷静に判断することが重要です。 いつ地震が発生してもよいように、住まいの耐震性を高める、備蓄を備えておくといった対策を取りましょう。 Q:地震発生後は保険や補助金を利用できますか? A:住宅が被害を受けた場合、地震保険や補助金(支援金)で修繕費の一部を補える可能性はあります。 さらに自治体によっては、建物の補修や建て替えに補助金制度が設けられている場合もあります。 ただし、すぐに保険金や支援金が出る訳ではなく、また全額が賄えるわけではありません。 加入している保険内容を事前に確認し、自治体の支援制度もチェックしておくと安心です。 Q:日常生活での不安を減らす方法はありますか? A:地震への不安は「備え」を整えることで和らぎます。 家具の固定や防災グッズの準備、家族での避難訓練といった対策が効果的です。 また、ハザードマップを活用して地域の危険を把握しておくことも重要です。 これから新築する、または建て替えやリフォームを検討中の場合は、耐震等級3の仕様への適合や鉄筋コンクリートなど、耐震性、耐久性の高い仕様にすることをおすすめします。 ▶関連コラム:「地震が怖くて家が買えない」5つの不安と理由を紹介│建物、その他12の対策も解説 まとめ|地震への不安は具体的な対策で備えよう ▶重厚感のあるコンクリートが際立つモダンな外観。そして、大人のプレミアム空間がある、高台に悠然と佇む家。【静岡市 新築注文住宅】 「最近地震が多い」と感じる場合、緊急地震速報やSNSによる、地震に関する情報の増加が影響している可能性があります。 一方で実態としては過去と比べて、地震の回数が大きく増えているわけではありません。 ただし、首都直下地震や南海トラフ地震といった巨大地震のリスクは日本に住んでいる以上は常に存在します。 だからこそ大切なことは、正しい知識と具体的な対策です。 耐震基準を満たした住まいづくりや家具の固定、ハザードマップの確認など、日常に取り入れられる備えを積み重ねることで、不安を「安心」に変えることが可能です。 過去の大地震でも「無傷」の実績を誇る百年住宅では、鉄筋コンクリート造による高い耐震性と耐久性を兼ね備えた住まいをご提供しています。 安心して長く暮らせる家づくりをご検討の方は、ぜひ百年住宅へご相談ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現
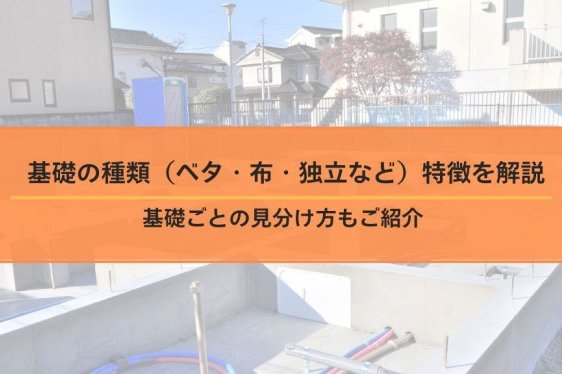
「基礎の種類にはどんな違いがありますか?」 家づくりを検討する方の中には、こうした疑問を抱く方もいらっしゃいます。 建物を支える基礎は、見えない部分でありながら耐震性や耐久性を左右する重要な構造体です。 布基礎・ベタ基礎・独立基礎・杭基礎など、選ぶ基礎によってコストや性能は大きく変わります。 本記事では、代表的な基礎の種類と特徴、さらに見分け方や工事の流れまでわかりやすく解説しますので、安心できる家づくりの参考にしてください。 ▶関連コラム:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 基礎とは?住宅など建物における役割を解説 建物の足元にある「基礎」は、普段は注目することの少ない部分ですが、家の寿命や安全性を大きく左右する重要な要素です。 はじめに、基礎はどのような働きを持っているのか確認します。 基礎の定義と機能、重要性 基礎とは、建物の荷重を地盤に伝えるための、コンクリート製の構造体を指します。 家そのものを支える要素であり、壁や屋根などの重量をバランスよく分散し、不同沈下や傾きを防ぐ役割を担います。 また、地面からの湿気やシロアリの侵入を防ぐ機能も備えており、建物を長く快適に使うためにも軽視できません。 つまり基礎は「建物を支える」「環境(湿気や害虫など)から守る」という二重の役割を持つ、重要な部分といえます。 基礎が建物の耐震性や耐久性を左右する理由 ▶百年住宅の住まいはダブル配筋・200mmの大型で安心 建物がどれだけ強固に設計されていても、その力をしっかりと地盤へ伝えられなければ耐震性は発揮できません。 基礎は地震時の揺れを受け止め、建物全体に加わる力を地面へと分散させる役割を担っています。 また、強度の高い基礎は地震の衝撃を受け止め、建物の損傷や倒壊を防ぐ効果を発揮します。 さらに、コンクリートの厚みや鉄筋の組み方といった基礎の仕様は耐久性に直結します。 正しい基礎の選択と施工が、住まいを長く安全に保つ重要な要素といえます。 基礎の種類と特徴を解説 基礎には複数の種類があり、それぞれ構造や適した地盤、費用に違いがあります。 ここからは代表的な3種類の基礎と、これらの基礎をさらに強固にする「杭基礎」ついて特徴を整理します。 布基礎(ぬのきそ) 布基礎は、建物の壁や柱の下に連続して鉄筋コンクリートを打設する基礎です。 住宅で広く採用されている工法で、必要な部分だけにコンクリートを用いるためコストを抑えられる点が魅力です。 また、後ほど解説するベタ基礎よりも、一般的には深い位置まで基礎を構築しますので、揺れに対する抵抗力が上がりやすい特徴があります。 一方、建物の重量が部分的に地盤へ伝わるため、地盤が弱い場所では不同沈下のリスクが生じます。 施工性が高く、比較的軽量な建物や安定した地盤での住宅建築に向いている基礎といえるでしょう。 ベタ基礎 ベタ基礎は、建物の底面全体を鉄筋コンクリートで覆う工法です。 建物の荷重を面で支えるため、安定した地盤上では高い支持性能を発揮します。 また、床下全体をコンクリートで覆うため。湿気やシロアリの侵入を防止しやすいというメリットもあります。 一方で、ベタ基礎は構造上自重が重く、また接地面も広いことから、地盤の深いところまで荷重が伝わりやすい点も特徴的です。 このため布基礎よりも慎重な地盤調査(ボーリング調査や標準貫入試験など)が求められます。 また、布基礎に比べてコンクリートの使用量が多く、施工費用が高くなる傾向があります。 布基礎とベタ基礎はよく比較されることがありますが、どちらも優れている点はありますので、地盤条件に合う工法を選ぶことが重要です。 独立基礎 独立基礎は、建物の主要な柱の下だけに四角いコンクリートを配置する工法です。 部分的に荷重を支えるため、軽量な建物や小規模な構造物に多く使われています。 施工が比較的簡単でコストも低い反面、建物全体をバランスよく支えるには不向きです。 そのため住宅よりも、カーポートや小屋、物置など小規模建築物に適しています。 適用範囲は限られますが、簡易性や経済性を優先する場面で選ばれる基礎です。 杭基礎 ▶軟弱地盤への適切な対応で安心の百年住宅の家 杭基礎は、建物本体を支える「布基礎、ベタ基礎、独立基礎」とは異なり、基礎を支える役割を持ちます。 長い杭を地中深くに打ち込み、地盤の堅固な支持層まで建物の荷重を伝える工法です。 軟弱地盤や液状化リスクのある地域でも安定した支持力を確保でき、大型建築やマンションに多く採用されています。 一般住宅でも、軟弱地盤では柱状改良や鋼管杭など杭基礎が選ばれるケースがあります。 ただし、施工には高度な技術とコストが必要で、工期も長くなる傾向があります。 地盤条件によっては不可欠となる、信頼性の高い基礎です。 なお、基礎は種類だけに注目するのではなく、確実な地盤調査を行い、その地盤に適した基礎設計を行うことが重要です。 たとえば、利用されることの多い簡易的なSWS試験に加えて、ボーリング調査や標準貫入試験を利用した、土質や支持層、液状化リスクまで確認できる体制にすることが望まれます。 百年住宅では地盤調査結果に基づき、建物全体で耐震性能を最適化していますので、地盤から耐震性の高い家を求めている方は、ぜひお気軽にご相談ください。 建物の基礎の見分け方 ▶建物を支える基礎部分にこだわる百年住宅の家 基礎は外観や床下の構造を確認することで、ある程度種類を見分けることができます。 布基礎やベタ基礎は住宅で多く採用され、独立基礎や杭基礎は用途や地盤条件に応じて選ばれます。 それぞれの特徴を理解しておくと、中古住宅の確認や新築時の施工精度のチェックに役立ちます。 布基礎:建物の壁や柱の下に帯状にコンクリートが立ち上がる。断面は逆T字型に見えることが多い。床下点検口から確認し地面がむき出しの場合は布基礎の可能性が高い。 ベタ基礎:建物の底面全体がコンクリートで覆われ、床下が一面コンクリートになっている。ただし、近年は布基礎でも防湿やシロアリ対策にコンクリートが打設されていることもあるので要注意。 独立基礎:柱の下だけに四角いコンクリートの塊があり、小規模建物やカーポートなどに多い。 杭基礎:地中深くまで杭を打ち込み支持層に荷重を伝えるため、外から直接は見分けにくく、設計図や施工記録で確認する。 基礎工事の流れをご紹介 基礎工事は、建物の強度や耐久性を左右する重要な工程です。 どういった流れで施工されるのか確認すれば、設計や施工への安心感につながりますので把握しましょう。 ①地縄張り、遣り方出し:建物の位置や高さを正確に示す作業。 ②掘削工事(根切り):基礎をつくるために地盤を掘り下げる。 ③砕石敷き、転圧:地盤を安定させる。防湿シートを敷くこともある。 ④捨てコンクリート:基礎の精度を高めるための下地コンクリート。 ⑤配筋工事:鉄筋を組み、耐久性を確保。 ⑥型枠設置、コンクリート打設:基礎の形をつくり、コンクリートを流し込む。 ⑦養生、型枠解体:強度を確保したうえで型枠を外し、基礎を仕上げる。 こうした工程を丁寧に施工することで、長期間にわたり、また大きな地震の発生時も安心して暮らせる住まいを建てられます。 基礎工事に関するよくある疑問Q&A 基礎工事は普段あまり目にする機会がなく、不安や疑問を感じる方も多いものです。記事の終わりに、代表的な質問に答えていきます。 Q:布基礎とベタ基礎はどちらがよいですか? A:布基礎はコストを抑えやすく、根入れが深いことで地表面の揺れに強い特徴があります。 一方でベタ基礎は建物全体を面で支える構造のため、安定した地盤上では優れた支持力を発揮します。 いずれの基礎も「どちらが優れている」という単純な比較ではなく、建物の規模や地盤の性質に応じて最適な基礎を設計し、建物全体の耐震バランスを取ることが重要です。 安易に「ベタ基礎だから安心」と考えるのではなく、地盤調査の内容と構造計算の根拠を確認しましょう。 Q:基礎断熱は基礎工事と関係ありますか? A:基礎断熱とは、基礎の立ち上がり部分や床下を断熱材で覆う工法です。 工事の段階から計画され、基礎の施工方法と密接に関わります。 床下の温度環境を安定させ、冬場の寒さや結露を防ぐ効果がありますが、換気や防蟻対策とのバランスが重要です。 ▶WPC工法だからできる、床下のない住まい なお、百年住宅の家は床下を土で充填、転圧したあとコンクリートを被せて岩盤化します。 床下をなくすことで、床下空間を冷たい風が吹き抜けることもなく、またシロアリやゴキブリといった虫の侵入を防ぐことが可能となります。 Q:シロアリや湿気に強くするにはどうすればいいですか? A:床下をコンクリートで覆うベタ基礎は湿気やシロアリ被害を防ぎやすい基礎です。 加えて、防湿シートの設置や床下換気、薬剤処理などを組み合わせることで効果が高まります。 なお、布基礎であっても地面が露出した箇所にコンクリートを打設することで、ベタ基礎と同様に、湿気やシロアリを防ぐ効果を期待できます。 Q:地震、地震後の不同沈下に強くしたいのですが? ▶入念な地盤調査・補強で安心の百年住宅の家 A:不同沈下を防ぐには、まず地盤調査で支持力を確認し、必要に応じて地盤改良や杭基礎を採用します。 地耐力が不足する箇所に対して深く基礎を設けるなど、適切な対応によって不同沈下が発生する可能性を抑えることが可能です。 また、基礎を構築する鉄筋やコンクリートといった部材を適切に利用する、施工精度も強固な基礎を作るために重要な要素です。 Q:基礎工事中に確認したいチェックポイントはありますか? A:配筋が図面通りに組まれているか、防湿シートに破れがないか、コンクリートの打設が均一かといった点が重要なチェックポイントです。 また、雨天時の打設や養生不足は強度に影響します。現場で確認が難しい場合は写真記録を残してもらい、施工品質を担保することが安心につながります。 まとめ|地震に強い基礎の家は百年住宅へ ▶『海を眺めながら暮らしたい。』を叶える、屋上に津波シェルターの付いた“津波に強い家”【静岡市】 建物の基礎は、布基礎・ベタ基礎・独立基礎・杭基礎といった種類ごとに特徴があり、選択を誤ると耐震性や耐久性に大きな差が生まれます。 適切な基礎を選び、正しく施工することが、安心して長く住める住まいを実現する第一歩です。 「百年住宅」では、過去の大地震でも倒壊や損壊を免れた実績を持つ鉄筋コンクリート住宅を提供しています。 さらに、床下を土で充填、転圧し、その上をコンクリートで岩盤化する独自工法により、シロアリ・湿気・不同沈下といったリスクも根本から解消。 強靭な基礎と構造体が「無傷の実績」を支えています。 地震に強い基礎と構造を備えた家づくりをお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現
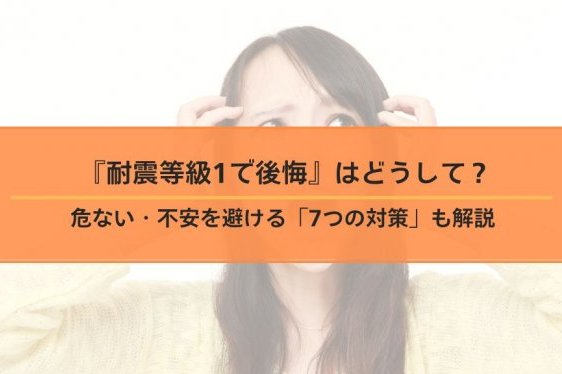
耐震等級1の家に住んでいて「本当に地震で倒れないのか」と不安や後悔を感じるケースがあるようです。 実際、建築基準法で定められた最低限の基準を満たす耐震等級1の家では、地震による倒壊や損傷への不安から「耐震等級1にして後悔した」という声も少なくありません。 本記事では、耐震等級と耐震基準の違いを整理しつつ、耐震等級1で後悔や不安を抱く理由をわかりやすく解説します。 さらに、そうした不安を払拭するための「7つの対策」もご紹介しますので、安心できる住まいを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 耐震等級とは?基準との違いもご紹介 家づくりを考える際によく耳にする「耐震基準」と「耐震等級」。似ているようで実は役割が異なり、混同しやすい点でもあります。 どういった違いがあるのか、確認しましょう。 耐震基準:法律で定められた最低限の耐震性 耐震基準とは、建築基準法によって定められた、建物の最低限の耐震性能を指します。 具体的には「震度6強から7程度の地震でも倒壊、崩壊しないこと」を基準に設計されます。 あくまで「命を守る最低限」の水準であり、建物が無傷で残ることまでは保証していません。 つまり、倒壊は免れても損傷を受ける可能性は十分にあり、繰り返し発生する地震への耐性も限定的だと理解しておく必要があります。 耐震等級:耐震基準を元により高い耐震性を求める指標 耐震等級は、耐震基準を基準として「より高い安全性を数値で示す指標」です。 等級は1〜3に分かれ、耐震等級1が建築基準法と同等の性能、2はその1.25倍、3は1.5倍の耐震性能を備えています。 等級が上がるほど地震に強く、繰り返しの揺れにも耐えやすくなります。 また、等級は住宅性能評価機関による認定制度で規定されますので、客観的な性能証明として資産価値や保険、ローン優遇を受けられることもメリットです。 耐震等級1で後悔や不安を感じる理由 耐震等級1は建築基準法と同等の最低限の基準ですが、住んでから「想像以上に不安」と感じる方は少なくありません。その理由を整理します。 繰り返し発生する地震に弱いことが分かった 耐震等級1は「一度の大地震で倒壊しないこと」を基準としていますが、繰り返しの地震には対応できるとは限りません。 実際、熊本地震では1回目の震度7で持ちこたえた建物が、2回目の強い揺れで倒壊する事例が見られました。 つまり、最低限の基準を満たしていても「複数回発生する揺れに弱い」ことが現実的なリスクなのです。 この点を理解せずに建ててしまい、後から不安を抱える人が多くいます。 ▶関連コラム:「地震が怖くて家が買えない」5つの不安と理由を紹介│建物、その他12の対策も解説 倒壊しない=安心ではない、損傷リスクを知った 耐震等級1は「命を守るために倒壊を防ぐ」ことを目的としています。 しかし、倒壊を免れても柱や壁が損傷し、住み続けられないケースは少なくありません。 大きな修繕費用が発生したり、一時的に避難生活を余儀なくされる可能性もあります。 「倒壊しなければ安心」というイメージと、実際の生活被害とのギャップが後悔につながる理由です。 資産価値が下がりやすく、売却時に不利であることを知った 住宅の資産価値は耐震性能によっても評価されます。 耐震等級1は最低基準ですので、等級2や3を取得した住宅と比べて市場価値が下がりやすく、売却や賃貸に出す際に不利になりやすいことが現実です。 特に中古住宅市場では「耐震等級3の認定」が購入検討者に安心感を与えるため、差が出やすい傾向があります。 購入後にその事実を知り「もっと高い等級を選んでおけばよかった」と後悔する人も少なくありません。 地震保険料や住宅ローンの優遇措置を知った 耐震等級は地震保険料の割引や住宅ローンの優遇制度と関係しています。 耐震等級2や3を取得した住宅は保険料の割引率が高く、フラット35などの金利優遇措置も利用できる場合があります。 一方で耐震等級1は優遇制度の対象外となるため、長期的には経済的負担が増える可能性があります。 後からこの事実を知り「初期費用を抑えるよりも、優遇制度を活用した方が得だった」と気付いて後悔する人も多いのです。 耐震等級1の後悔や不安を払拭する「7つの対策」を解説 では、耐震等級1を選んで後悔や不安をすることを避けるには、どうすればよいのでしょうか。 主な7つの対策をお伝えします。 耐震等級3適合の家を建てる コンクリート・箱型など構造にも注目する 共振対策を施した住宅を選ぶ 基礎や地盤に対する補強を施す 火災や津波など二次災害に備えた家づくりをする 地震保険の利用など経済面での対策を立てる 過去の地震で損傷しなかった実績のある会社に依頼する 耐震等級3適合の家を建てる これから新築を検討するなら、有効な対策のひとつは「耐震等級3」に適合した家を建てることです。 耐震等級3は建築基準法の1.5倍の耐震性能を持ち、震度7クラスの地震にも強いとされます。さらに、地震保険や住宅ローン優遇制度などの対象にもなり、長期的な経済面でのメリットも大きいです。 家族の安全と資産価値を守るためには、初期コストを抑えるよりも等級3を選ぶ方が安心につながります。 コンクリート・箱型など構造にも注目する 耐震性は等級だけでなく「構造」にも大きく左右されます。 ▶どの方向からの外力にも強い、百年住宅のWPC工法(箱型構造) 例えば、鉄筋コンクリート造や壁式構造など、強固な構造や建物全体を箱型で支える構造は揺れに強い特徴があります。 木造住宅でも、耐力壁をバランス良く配置したシンプルな四角形の間取りにすることで耐震性能を高められます。 地震に強いとされる「素材」と「形」を選ぶことで、耐震等級1でも不安を減らすことが可能です。 ▶関連コラム:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介 共振対策を施した住宅を選ぶ 建物には固有の揺れの周期があり、地震波と一致すると「共振」が起こり、揺れが増幅してしまいます。 共振現象の発生を避けるためには、地震による揺れと建物が持つ「固有周期」が合致しないよう家を建てることが効果的です。 ▶共振現象の発生を防ぐ、百年住宅のWPC工法の家 たとえば、一般的な地震の揺れよりも固有周期が短い鉄筋コンクリート製の家を建てることで、地震と周期が合い共振が発生することを避けられます。 ▶関連コラム:地震による共振とは?仕組みと被害の実例、共振を防ぐ5つの対策まで解説 基礎や地盤に対する補強を施す どんなに建物の耐震性を高めても、地盤や基礎が弱ければ被害は避けられません。 特に軟弱地盤や液状化リスクのある地域では、地盤改良や杭基礎など、建物の地盤や基礎を強化する対策が重要です。 ▶軟弱地盤に対応する、強固な地盤補強 既存住宅で不安がある場合も、基礎の補強工事や耐震診断を行うことで安全性を高められます。 耐震等級1の家であっても、地盤から建物を支える工夫を施せば、後悔を減らす大きな対策となります。 火災や津波など二次災害に備えた家づくりをする 地震そのものに耐えられても、火災や津波といった二次災害に弱ければ安心はできません。 外壁や屋根を、鉄筋コンクリートなど耐火性の高い素材にする、防火地域に対応した設計にする、あるいは高台や避難経路を意識した立地を選ぶことが大切です。 ▶屋上に津波避難シェルター、津波の被災予想区域でも命を守る百年住宅の家 また、津波被害が想定される地域では、屋上避難が可能なプランも有効です。 耐震等級1の弱点を補うには、地震と関連して発生するリスクも視野に入れた家づくりが欠かせません。 ▶関連コラム:南海トラフ地震が起こるとどこが危ないのか|県やエリア・対策も解説 地震保険の利用など経済面での対策を立てる 建物に対する地震対策に加えて、経済的な備えを整えておくことでも安心は得られます。 耐震等級が低い住宅でも、地震保険に加入しておけば被災後の修繕費や再建費用を補える可能性があります。 さらに、金融機関の災害時の返済猶予制度などを事前に把握しておくことも有効です。 そもそも地震の発生時に損傷が生じず、地震後に経済的な損失を受けない住まいづくりも重要です。 ▶大地震でも安心「無傷の住まい」が分かるカタログ4点セットはコチラ 過去の地震で損傷しなかった実績のある会社に依頼する 家を建てる際の依頼先選びも重要です。 過去の大地震で建てた住宅が無傷、または軽微な損傷にとどまった実績を持つ会社は、設計力や施工技術が信頼できる証拠です。 実際の施工事例や被災後の調査報告を確認することで、安心して任せられるかを判断できます。 耐震等級1であっても「どの会社が建てたか」によって強さが異なるため、依頼先の見極めが後悔を防ぐ大きな鍵となります。 ▶過去の震災で「無傷」の実績を持つ百年住宅の家 まとめ|耐震性の高い安心の住まいは「百年住宅」まで ▶30畳の大空間LDKと富士山が見える屋上ジャグジーのある家【沼津市】 耐震等級1は建築基準法に適合した最低限の耐震性能にすぎず、繰り返し起こる地震や二次災害、資産価値の面で後悔や不安を抱くケースが少なくありません。 安心して長く暮らすためには、耐震性の高い構造、地盤への対策、経済的な備えなど多角的な工夫が欠かせません。 百年住宅では、鉄筋コンクリート造をはじめとした、高い耐震性と耐久性を誇る住まいを提供しています。 過去の大地震でも「無傷」を実証した実績があり、命と暮らしを守る確かな安心をご提案可能です。 「地震に強い家づくり」を検討される方は、ぜひ百年住宅までご相談ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現

「日本で地震が多い県はどこだろう」と疑問に思う方は多いでしょう。 日本は世界有数の地震大国ですが、都道府県ごとに発生件数やリスクの度合いに違いがあります。 実際に地震の多い県では、小さな揺れから大規模地震まで頻繁に発生しており、住まいや暮らしに影響を与えています。 本記事では、最新データに基づいた地震が多い県ランキングと、その理由や特徴、さらに安心して暮らすための対策についても解説します。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 日本で地震が多い県ランキング(震度4~) はじめに多くの方が気になる、日本で地震が多い都道府県をランキング形式でご紹介します。 なお、今回は気象庁の震度データベース検索から以下の条件で抽出しています。 観測期間:2015年8月24日から2025年8月23日(過去10年間) 対象震度:震度4以上 1:熊本県 156回 2:鹿児島県 110回 3:石川県 91回 4:茨城県 80回 5:北海道 77回 6:福島県 70回 7:栃木県 51回 8:宮城県 49回 9:千葉県 47回 10:岩手県 37回 ▶参考:気象庁 震度データベース検索 過去10年を対象とした場合、置物が倒れるなど被害が生じ始める震度4以上の揺れを観測した都道府県は、熊本・鹿児島・石川の3県で回数が多い結果となりました。 このうち熊本県は熊本地震が、鹿児島県はトカラ列島近海での地震が、石川県では能登半島沖地震が回数を引き上げる要因となっています。 また、東日本大震災のあった2011年を観測期間に加えると、福島県の回数が最も多くなります。 このように、地震は一度発生した地域で一定期間複数回発生する傾向にありますので、「回数が少ないから安心」「回数が多いから用心する必要がある」とは思わず、日本で暮らす以上どの地域で暮らす場合でも突然発生する地震へ備える必要があります。 ▶関連コラム:愛知県は地震が少ない?2つの理由を解説│過去の地震歴、災害リスクと安心できる暮らし方も紹介 日本で地震が多い理由をご紹介 ▶引用:気象庁 地震発生のしくみ 日本で地震が多い理由は、国土の地理的な条件と地殻構造が関係しています。 日本列島は複数のプレート境界に位置しており、常に大きな力が加わっています。 また、全国に活断層が分布していることや火山活動の影響も重なり、各地で地震が発生しやすい環境が整っているのです。 主な理由をまとめると次のとおりです。 プレート境界に位置する:4つのプレートがせめぎ合う場所にある 活断層が多い:内陸直下型地震の要因となる 火山活動が活発:マグマの動きが地震を誘発する場合がある 地殻変動が頻発:プレートの沈み込みや隆起が継続的に起こる このように、日本は地震のリスクが常に存在する特殊な環境にあるのです。 地震が多い日本で暮らすための7つの備え いつどこで地震が発生してもおかしくない日本において、揺れに対しても安心して暮らすためには、事前の備えが重要です。 どういった対策を取るべきなのか、具体的な方法をご紹介します。 耐震、制震、免震など地震への揺れ対策を施す 家具や家電の転倒対策を検討する 地震による津波、火災への対策を施す 住まいの耐久性を高める対策を検討する 被災後の経済的な負担を解消する方法を検討する お住まいのエリアの被災の予測を確認する 防災グッズや備蓄、避難について検討する 耐震、制震、免震など地震への揺れ対策を施す 大地震に備えるには、まず住まい自体の耐震性を高めることが重要です。 新築では耐震等級3を満たす設計に加え、揺れを吸収する制震ダンパーや、建物に地震動を伝わりにくくする免震装置を取り入れるとより安心です。 ▶過去の大地震でも"無傷"の実績、百年住宅の家 さらに、過去の大地震において被害を受けなかった住宅の「実績」があるかどうかも大切な判断基準です。 信頼できる実績を持つ構造や工法を選ぶことで、倒壊リスクを大幅に抑えられます。 ▶関連コラム:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介 家具や家電の転倒対策を検討する ▶引用:内閣府 できることから始めよう!防災対策 強い揺れによるケガを避けるためには、家具や家電の転倒対策を検討することが重要です。 大型家具はL字金具や突っ張り棒で壁や天井に固定し、冷蔵庫やテレビは耐震マットやベルトを利用しましょう。 寝室では重い家具を置かない、避難経路となる廊下には物を置かないといった配置の工夫も効果的です。 こうした対策でケガを防ぐだけでなく、避難の妨げを減らすことができます。 地震による津波、火災への対策を施す 沿岸部に家を建てる場合は、地震直後の津波避難経路や高台の確認が欠かせません。 万が一に備えて自治体指定の津波避難ビルも把握しておきましょう。 ▶構造体自体が耐火性能、百年住宅の家 また、都市部では耐火性能の高い外壁材や防火戸の採用が揺れのあとの火災対策に有効です。 大地震では揺れそのものに加え、津波や火災といった二次災害の被害が拡大しやすいことから、事前の備えが生死を分けることになります。 住まいの耐久性を高める対策を検討する 地震に強い家を長く保つためには、耐久性のある素材や構造を選ぶことも大切です。 鉄筋コンクリート造など、揺れに強く劣化しにくい住宅は安心感があります。 また、木造住宅でも防蟻処理や防水処理を徹底し、柱や土台の劣化を防ぐことが重要です。 ▶幅広、ダブル鉄筋で住まいを支える、百年住宅の家 さらに、地盤の補強や基礎部分の強化(例:ダブル配筋や厚みを増した基礎)を行うことで建物全体の安定性を高め、地震時の損傷を大幅に軽減できます。 ▶関連コラム:【鉄筋コンクリートの家】8つのメリット、5つのデメリット│後悔する瞬間と対策も解説 被災後の経済的な負担を解消する方法を検討する 地震で被害を受けた場合、再建費用や仮住まいの負担が家計に影響します。 その備えとして、地震保険などお住まいに対する経済的な対策が有効です。 火災保険だけでは地震被害は補償されないため、地震保険との併用が必須といえます。 加えて、自治体や国の住宅再建支援制度、補助金を事前に確認しておくことも重要です。 ▶地震後の修繕費を"0円"に、地震でも無傷の実績を持つ百年住宅の家 さらに、鉄筋コンクリート造など、そもそも損傷しづらい構造を選ぶこと自体が経済的負担を減らす最善策となります。 この点でも、ハウスメーカーごとの過去の地震に対する損傷の実績を確認することが重要といえます。 お住まいのエリアの被災の予測を確認する 自分の暮らす地域がどのような地震被害を想定しているのかを知ることは、防災の第一歩です。 自治体が公開しているハザードマップを確認し、津波・液状化・土砂災害などのリスクを把握しておきましょう。 特に新築や購入を検討している場合は、立地選びにも直結する重要な情報です。 日常的に意識することで、避難計画や備蓄などの備えも具体的に計画できます。 ▶関連コラム:南海トラフ地震が起こるとどこが危ないのか|県やエリア・対策も解説 防災グッズや備蓄、避難について検討する 大地震ではライフラインが止まる可能性が高いため、水や食料は家族分で最低3日分、可能なら1週間分を備蓄しておきましょう。 あわせて簡易トイレ、懐中電灯、モバイルバッテリーなども必須です。 避難所に行く場合は持ち出し袋を準備し、家族で避難場所や連絡方法を共有しておくことが重要です。 これらの準備があることで、発災直後の混乱を大幅に減らすことができます。 地震の多い県についてのQ&A 地震が多い県に暮らすとなると、不安や疑問は尽きません。 被災予想地域で聞かれることの多い、住まいや安全対策に関する3つの質問にお答えします。 Q.地震が多い県に住むことは危険ですか? A.地震に遭遇するリスクは高くなりますが、必ずしも危険とは限りません。 たとえば鉄筋コンクリート造で、過去の大地震でも損傷しなかった実績を持つ住宅であれば、強い揺れでも倒壊リスクを大幅に抑えられます。 さらに、防災グッズや避難経路の確保、地震保険の加入などを組み合わせることで、地震の多い地域でも安心して暮らすことは十分に可能です。 ▶「地震に無傷」で被災時の経済的不安を解消、百年住宅の家 Q.古い家でも地震対策は可能ですか? A.古い家でも地震対策は可能です。 まずは耐震診断を受け、基礎や構造の弱点を把握しましょう。 その上で、耐震補強工事や制震ダンパーの設置を行えば、旧耐震基準の住宅でも安全性を高められます。また、柱や土台の防蟻・防水処理を施して劣化の進行を止めることも有効です。 ただし、劣化の進行状況や建物の状態によっては、補強では限界があり、建て替えを検討することが確実な対策となる場合もあります。 Q.今後発生する可能性のある大きな地震は? A.専門家が警戒するのは、南海トラフ地震(東海~九州沿岸部)や首都直下地震(関東南部)です。 ▶引用:内閣府 想定される大規模地震 いずれも今後30年以内に高い確率で発生すると予測されており、発生すれば甚大な被害が想定されています。 そのほか、東北から北海道にかけての太平洋側や中部・近畿圏、そのほか各地の活断層での地震が発生する可能性もありますので、場所を問わず日本に住む以上はどこに住む場合でも常に備えが必要です。 まとめ|地震の多い県での家づくりは「百年住宅」へ ▶大理石風外観とモミジを眺めるお気に入りLDK空間のある上質な和モダンの家【静岡市・新築注文住宅】 日本は世界でも有数の地震大国です。 過去10年では熊本県・鹿児島県・石川県といった地域で地震が多かったものの、どの地域で地震が発生してもおかしくない状況です。 家具の固定や備蓄といった生活面の対策に加え、根本的には「壊れにくい家に住むこと」が最も大切です。 特に鉄筋コンクリート造のように、過去の大地震でも損傷を免れた実績のある住宅を選ぶことは安心につながります。 百年住宅は、鉄筋コンクリートを利用したWPC工法と長期保証で「無傷の住まい」を実現してきました。地震への不安を根本から解消したい方は、ぜひ一度ご相談ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現
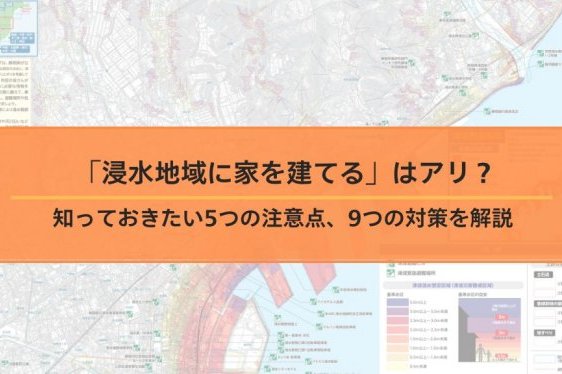
近年、台風や豪雨による水害が全国各地で増え、浸水地域での家づくりに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 また、地震で発生する津波による浸水が気になる方も多いものです。 そこで本記事では「浸水地域に家を建てても大丈夫なのか?」という疑問にお答えします。 浸水地域で家を建てることのメリット・デメリットといった特徴に加え、建築時に押さえておきたい注意点や、被害を最小限に抑えるための具体的な対策まで解説します。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 浸水地域に家を建てても大丈夫?基礎知識をご紹介 浸水地域での家づくりについて確認する前に、そもそも浸水地域とは、どういった地域を指すのか確認しましょう。 浸水地域とは?定義を確認 浸水地域とは、市町村や国が作成する、「津波浸水想定区域図」や「洪水浸水想定区域図」、「高潮浸水想定区域図」といった地図で指定されるエリアを指します。 想定される浸水深や範囲は、過去の被害履歴や地形、降雨量などを基に算定されます。 指定区域に含まれる場合、防災計画や建築条件にも影響しますので、家づくりや土地選びの段階で浸水予想範囲を確認しましょう。 浸水深別の被害イメージ(50cm・3m・5m) 津波や洪水、高潮の被害は、被災した場合の浸水する深さによって程度が変わります。 どの程度の深さが建物の1階、2階などの高さになるのか確認しましょう。 ▶引用:国土交通省 水害ハザードマップ作成の手引き 国土交通省が公表している「水害ハザードマップ作成の手引」によると、浸水深0.5mで建物1階が床上浸水を始める可能性があり、大人でも歩行や避難が困難になります。 3.0mでは建物2階床面まで浸水し生活機能がほぼ停止、長期避難や大規模修繕が必要になります。 5.0mになると2階が完全に水没、3階床面まで達する恐れがあり、建物全体が甚大な損害を受けます。 こうした浸水深の違いは、避難計画や建築方法、土地選びの判断に直結するため、事前に必ず確認しておくことが重要です。 津波・洪水・高潮 建物被害の違い 浸水地域で家を建てる場合に注意したいポイントは、津波と洪水、高潮といった水害には、発生要因や被害の広がり方に違いがある点です。 以下のような特徴を確認して、建物の設計や土地選びに活かしましょう。 津波:地震によって発生、短時間で大水圧と漂流物を伴い押し寄せる。浸水深が浅くても破壊力が強く、建物自体が流出する危険性がある。 洪水:河川の氾濫によって発生、比較的緩やかに水位が上昇する。長時間の浸水によって床下、構造部に水が染み込み、腐食やカビが発生する可能性がある。 高潮:台風や低気圧による海面上昇によって発生、洪水と特徴は似ているものの、塩害を伴うことから金属製品や設備機器への異常にも注意が必要。 ▶関連コラム:南海トラフ地震が起こるとどこが危ないのか|県やエリア・対策も解説 浸水地域に家を建てるメリット 津波や洪水、高潮などの不安がある浸水地域ですが、家を建てる場合は次のようなメリットも存在します。 土地価格が比較的安い 利便性の高い立地が多い(駅や中心部に近い) 景観や自然環境に恵まれている場合がある 災害に対応したインフラ整備や防災対策が進んでいることも 特に土地価格の安さは大きな魅力で、同じ予算でも広い敷地や好立地を確保できる可能性があります。 また、海辺や河川沿いは眺望や開放感があり、暮らしに潤いを与えてくれます。 さらに近年は、堤防強化や排水ポンプ場の整備など、防災インフラが向上している地域も多く、安全性が過去より改善されているケースも見られます。 浸水地域に家を建てるデメリット 一方で、浸水地域での家づくりには次のようなデメリットもあります。 水害発生時の被災リスクが高い 火災保険の水災補償、地震保険が高額になりやすい 住宅ローン審査や担保評価に不利になる場合がある 将来の資産価値や売却のしやすさに影響する 最大のリスクは、水害による直接的な被害です。 浸水で構造体や設備が損傷すれば修繕費用が必要になり、また長期の避難を強いられる可能性があります。 また、水災補償を付けると保険料が高くなり、住宅ローン審査でも担保評価が下がる可能性があります。 売却時には買い手が限られ、価格交渉で不利になるケースも少なくありません。 浸水地域に家を建てる場合の注意点 こうした特徴を持つ浸水地域では、家を建てる前に次の点を確認しましょう。 津波、洪水、高潮など災害の種類を確認する 低地、谷地、埋立地など地形条件を確認する 地盤の強度や液状化の発生リスクを確認する 将来の資産価値や売却しやすさを確認する ライフラインの停止についても予測する まず災害の種類を把握し、その地域が津波や洪水、高潮のいずれに脆弱なのかを確認します。 加えて地形条件や標高差を調べ、低地や埋立地といった浸水リスクの高い土地を避けることが重要です。 新築を建てるにあたっては、地盤調査で強度や液状化リスクを確認することもおすすめです。 将来の資産価値は、水害リスクが高いほど下がりやすく、売却時に価格交渉で不利になる可能性があります。 また、浸水被害時には停電や断水、通信障害などライフラインが長期間停止する場合もあります。 こうした経済性や生活面での影響を踏まえて計画を立てることが大切です。 浸水地域に家を建てる、後悔を避ける9つの対策 浸水地域での家づくりでは、被害を最小限に抑えるための計画と備えが不可欠です。土地選びから構造、設備、資金対策まで総合的に検討しましょう。 ハザードマップで被災区域や浸水深を確認 同じ地域でもより高い土地を選択する 盛土や高基礎で浸水を避ける 2階リビングなど主要な間取りを高い位置に 浸水時も堅牢な構造(RCなど)を選択する 宅内に浸水用のシェルターを設置する 主要な設備を高い位置に配置する 十分な地盤調査と改良を施す 保険や住宅ローンの特約で金銭的に備える ハザードマップで被災区域や浸水深を確認 ▶静岡市 洪水ハザードマップ 家を建てる前には、国や自治体が公表するハザードマップで浸水の想定範囲や深さを確認しましょう。 津波や洪水、高潮、内水氾濫など災害の種類ごとのリスクを把握することで、立地や構造を判断する材料になります。 現地での確認や地元役場での情報収集を行い、過去の浸水履歴もあわせてチェックすると安心につながります。 同じ地域でもより高い土地を選択する 同じ地域でも標高差や地形条件により、浸水リスクは異なります。 できる限り周辺より高い土地を選べば、被害を軽減できる可能性が高まります。 地形図や測量データを参照しつつ、津波の到達範囲や雨水の流れ方、排水設備の状況も確認しましょう。 大雨の際に適切に排水を処理できていれば、建物の浸水を心配する必要はありません。 盛土や高基礎で浸水を避ける 浸水が想定される場合は、盛土による敷地のかさ上げや高基礎構造の採用で床面を高くし、浸水到達前に生活空間を守る工夫が必要です。 土木工事や擁壁工事は高額になる恐れがありますので、施工費用や工期は事前に見積もりを取り、予算計画に組み込みましょう。 完成後は排水計画との整合性を確認し、万が一の際にも水はけが悪化しないよう配慮が必要です。 2階リビングなど主要な間取りを高い位置に 浸水リスクに備えるなら、リビングやキッチンなど生活の中心となる空間を2階以上に配置する間取りがおすすめです。 被災時も居住性を確保でき、避難所に移らず一定期間生活できます。 階段や動線計画とあわせて快適性を保ち、バルコニーや避難経路も高所に確保しておくと安心です。 浸水時も堅牢な構造(RCなど)を選択する ▶重厚感のあるコンクリートが際立つモダンな外観。そして、大人のプレミアム空間がある、高台に悠然と佇む家。【静岡市 新築注文住宅】 水害に強い家づくりには、浸水でも構造体が損傷しにくい鉄筋コンクリート(RC)造などの堅牢な構造が有効です。 高い強度により修繕負担や資産価値の低下を抑えられます。 また、耐水性の高い仕上げ材を併用し、施工実績の豊富な業者に依頼することで、より安全性の高い住まいを実現できます。 ▶関連コラム:【鉄筋コンクリートの家】8つのメリット、5つのデメリット│後悔する瞬間と対策も解説 宅内に浸水用のシェルターを設置する ▶屋上に設置する津波避難シェルター 最近では、津波や洪水に対応した屋内シェルターの導入事例も増えています。 屋上や高所に避難できるスペースを確保すれば、避難所までの移動が困難な場合でも安全を保てます。 家族の人数や滞在日数に合わせた容量や設備を選び、食料や日用品、通信手段も備えておくと実用性が高まります。 主要な設備を高い位置に配置する 分電盤や給湯器、空調機器などの主要設備は、浸水想定よりも高い位置にまとめて配置します。 これにより水害時の損壊を防ぎ、復旧までの時間や費用を削減できます。 屋外設備は防水仕様を採用し、配線や配管もできる限り高所に集約しておくと安心です。 十分な地盤調査と改良を施す ▶入念な地盤調査・補強で安心の百年住宅の家 浸水地域では地盤が軟弱なケースが多く、液状化のリスクも無視できません。 建築前に地盤調査で性質を確認し、必要に応じて改良を施すことで、沈下や傾きによる被害を防げます。 地盤保証制度の活用や、改良工法のメリット・デメリットを比較検討して最適な方法を選ぶことが大切です。 保険や住宅ローンの特約で金銭的に備える 万一に備え、火災保険に水災補償、地震保険を追加し、住宅ローンにも自然災害時の返済免除や猶予の特約を付帯することも手段のひとつです。 こうした対策で被害後の経済的負担を大きく軽減できます。 契約前には補償範囲や条件、免責額を必ず確認し、複数社のプランを比較して最適な内容を選ぶことが重要です。 まとめ│浸水地域の新築は強固な構造の家で ▶『海を眺めながら暮らしたい。』を叶える、屋上に津波シェルターの付いた“津波に強い家”【静岡市】 浸水地域での家づくりは、立地や地形、地盤、浸水深などのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。 盛土や高基礎、間取りの工夫に加え、RC造など水害に強い構造を選べば被害を最小限に抑えられます。 さらに、設備の高所配置や保険加入など金銭的備えを整えることで万一の際も安心です。 強固な構造と入念な計画で、安全で快適な住まいを実現しましょう。 百年住宅は、耐震性・耐久性・耐水性に優れた鉄筋コンクリート住宅を提供し、浸水地域でも長く安心して暮らせる住まいづくりをサポートしています。 豊富な施工実績と専門知識をもとに、お客様一人ひとりの条件に合わせた最適な提案が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現
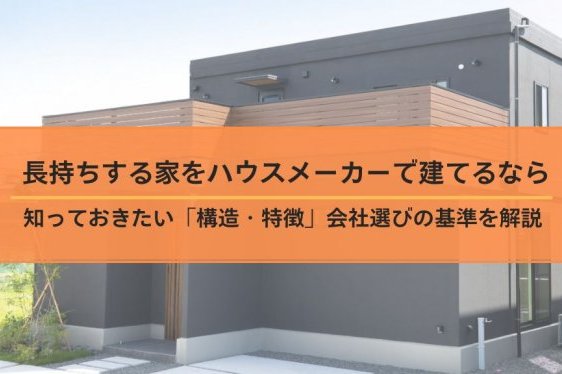
「長持ちする家を建てたい」 このように考える方は少なくありません。 せっかくのマイホームなら、家族が安心して長く暮らせる住まいにしたいものです。 そこで本記事では、そもそも長持ちする家とはどのような特徴を持つのかをわかりやすく解説します。 さらに、具体的なハウスメーカー選びの基準や、長寿命の住まいづくりのヒントをお伝えします。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 日本の住宅寿命はなぜ短いのか(欧米との比較) ▶参考:国土交通省 長持ち住宅の手引き はじめに、日本の住宅の寿命はどの程度なのか確認しましょう。実は、日本の住宅の寿命が短いことが長年指摘されています。 日本の住宅の平均的な寿命は約30年とされ、他の国と比較して短い特徴があります。 その理由は、「家を建てるなら新築がよい」という新築志向のほか、住宅のメンテナンス不足や、そもそも長期間の使用に耐えられない建材を利用している点も挙げられます。 一方で、木造の寺社仏閣が残っているように、頑丈な工法を選択し、定期的に費用をかけてメンテナンスを施せば、長寿命の建物(住宅)を建てることは可能であることも確かです。 耐久性が低い家に起こるリスク では、耐久性が低い住宅に住んだ場合、どういった暮らしになるのでしょうか。 耐久性が低い家に住む場合のリスクについて確認しましょう。 劣化が早いため強度低下により地震や台風などの災害時に損傷しやすい 外壁や屋根の劣化による雨漏り、腐食を受けやすい 断熱性、気密性が徐々に低下し、快適性や光熱費に影響を及ぼす 修繕費や建て替え費用が高くなる 資産価値が下落しやすい このように、短命の住宅に住むことは快適性を損なうことに加えて、居住者の命を脅かしたり、経済的な不安につながる恐れがありますので、必ず避けたいところです。 長持ちする家に住むメリット ▶シンプルだけど木の温もりを感じる【白と木の家】 効果的な木目の使い方に注目!【静岡市】 一方で耐久性の高い家は、次のようなメリットがありますので合わせて把握しましょう。 住宅ローンの完済後も長く住み続けられる 建て替えや大規模修繕の回数が減り、長期的なコストを削減できる 資産価値を維持しやすく、将来の売却時に有利になる 安全性や快適性を長く保てるため、家族の健康と安心を守れる 補助金や優遇制度の対象になる場合がある このように長持ちする家には複数のメリットがありますので、これから家を建てるなら「耐久性の高さ」といった視点を重視することをおすすめします。 長持ちする家にするための代表的な方法のひとつは、鉄筋コンクリート造など強固な構造を選ぶことです。 耐久性の高い家を求めている方は、過去に発生した大地震でも無傷の実績を持つ、鉄筋コンクリートを利用したWPC工法の百年住宅にぜひご相談ください。 ▶大地震でも安心「無傷の住まい」が分かるカタログ4点セットはコチラ 長持ちする家の5つの条件を解説 家を長く快適に保つためには、耐震性、耐久性、耐水性、メンテナンス性、可変性といった5つの条件を満たすことが重要です。 それぞれどういった特徴があるのか解説します。 耐震性が高い 地震大国である日本において、耐震性は住宅を長持ちさせる重要な要素のひとつです。 たとえば、耐震等級3の取得や地盤調査、地盤改良によって地震時の倒壊リスクを低減可能です。 また、RC(鉄筋コンクリート)造のように、高い剛性(変形しにくさ)を持つ家であれば地震による損傷や変形を避けられますので、より長寿命な家になることを期待できます。 耐久性の高い構造や素材 構造や素材の選択は住宅の寿命に直結します。 一戸建てなどの住まいは長期間住み続けることから、経年劣化しにくい材料を選ぶことが重要です。 たとえば屋根材は瓦やガルバリウム鋼板、外壁は磁器タイルや耐候性サイディングなど、直射日光や風雨による劣化に強い建材を採用すると効果的です。 さらに、鉄筋コンクリートのように素材としての強度が高く、ガルバリウム鋼板やサイディングよりも遥かに耐用年数が長い建材を利用することで、長期間強度を保てる住まいを建てられます。 ▶高強度なPCSパネルを利用したWPC工法 加えて、建物の「法定耐用年数」を確認することも、耐久性を検討する上で重要なポイントです。 法定耐用年数は継続して使用し続けられる年数を示していて、主に税金を計算する際に利用される考え方です。 木造住宅:22年 軽量鉄骨造:27年 重量鉄骨造:34年 鉄筋コンクリート:47年 ▶参考:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表 このように法定耐用年数を目安にして、長持ちする家の仕様を検討することも重要です。 耐水性、湿気対策が万全 住宅の劣化要因として大きい要素のひとつが水分です。 屋根や外壁の防水処理、ベランダやバルコニーの防水シート施工などで雨水の侵入を防ぐことが可能です。 また、床下換気や外壁通気層の設置により、基礎や壁の中に湿気を溜めない設計も重要です。 たとえば、断熱材に吸湿性の低い素材(硬質ウレタンフォームなど)を使い内部結露を防止、防蟻・防カビ処理を加えることで、水分による腐食や構造劣化を長期的に抑制できます。 ▶台風による雨も防ぐ百年住宅の家 メンテナンス性が高い設計 長く住み続けるためには、修繕や交換をしやすい設計が不可欠です。 耐候性の高い外壁材など、塗り替え頻度を抑えられる素材を選べば維持費を軽減できます。 また、配管や配線を点検口から容易に確認できる構造や、屋根勾配を適切に設計して雨水を効率的に排水する工夫も重要です。 点検や補修のしやすさは設備や建物の良好な状態を維持することになり、結果として住宅寿命を延ばすことにつながります。 ▶長期的な費用を抑えられる百年住宅の住まい 可変性のある間取り 家族構成やライフスタイルの変化に合わせて間取りを柔軟に変えられる設計は、長く住み続けるための重要なポイントです。 可動式の間仕切りや可変性を見越した壁配置など設計に配慮すれば、大規模リフォームを伴わずに住まいを更新できます。 さらに、水回りや収納の位置変更がしやすい配管、配線計画をあらかじめ整えておくことで、将来的な間取り変更や設備更新のコストも大幅に抑えられます。 長持ちする家を実現するには、紹介した耐震性、耐久性、耐水性、メンテナンス性、可変性といった条件が重要です。 こうした要素を十分に取り入れた住宅をご検討中の方は、過去の大地震も含めて倒壊ゼロの実績を持つ、WPC工法の百年住宅まで、お気軽にご相談ください。 ▶お家にいながら、倒壊ゼロの実績を持つ百年住宅に「オンライン相談」 長持ち住宅を実現するためのハウスメーカー選びの基準 長持ちする家を建てるには、構造、工法の選択、耐久性やメンテナンス性能の実績、そして保証やアフターサービスの充実度を比較検討することが大切です。 こうした総合力のあるハウスメーカーはどのように探せばよいのでしょうか。 構造と工法の検討 住宅の寿命は構造、工法によって左右されます。 具体的には次のような工法が代表的です。 木造(在来方法、2×4工法など):費用を抑えられ、リフォームなどの可変性が高い 鉄骨造:コストを抑えつつ一定の耐震性、耐久性が得られる RC造(鉄筋コンクリート):比較的費用は高いものの高耐久高耐震で安心感が高い 構造ごとの特性を理解し、希望する耐久性や性能に合った工法を選ぶことで、自然と最適なハウスメーカーの数が絞られます。 耐久性やメンテナンス性能の実績 長く快適に住むためには、メーカーが採用する素材や構造の耐久性、メンテナンス性の高さが重要です。 耐候性の高い外壁材や構造体など、経年劣化しにくい素材の採用実績や過去の施工事例、築後20年、30年の住宅の状態などを確認すると、将来の安心度が見極めやすくなります。 可能であれば検討中のハウスメーカーにおいて、建築から一定年数が経過したお住まいの状態や、地震や台風を受けたあとの状態を確認させてもらいましょう。 ▶百年住宅のWPC住宅は過去の大地震でも「無傷」 保証やアフターサービス体制の確認 長期保証制度や定期点検体制の充実度は、家の寿命を延ばすうえで欠かせません。 初期保証期間の長さや点検の頻度、保証延長の条件を比較し、必要時に迅速に対応できる体制か確認しましょう。 地震や台風、構造体の劣化など、どういった損傷を受けた場合に保証を受けられるのか、保証条件の確認をすることも重要です。 ▶初期35年、最長100年保証で安心の住まいに まとめ|長持ちする家は百年住宅にご相談を ▶『海を眺めながら暮らしたい。』を叶える、屋上に津波シェルターの付いた“津波に強い家”【静岡市】 長持ちする家を建てるには、耐震性、耐久性、耐水性、メンテナンス性、可変性といった5つの条件を満たすことが欠かせません。 さらに、信頼できるハウスメーカー選びやアフターサービス、適切な保証によって、数十年に渡り快適に暮らし続けられる安心の住まいを建てられます。 百年住宅は、耐久性の高い鉄筋コンクリート造を採用し、過去の大地震でも倒壊ゼロの実績を誇る長寿命住宅の専門メーカーです。 耐久性と耐震性に優れた構造に加え、将来を見据えた設計と徹底した品質管理で大切な住まいを守ります。 世代を超えて安心できる家づくりをお考えなら、ぜひ百年住宅にご相談ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現
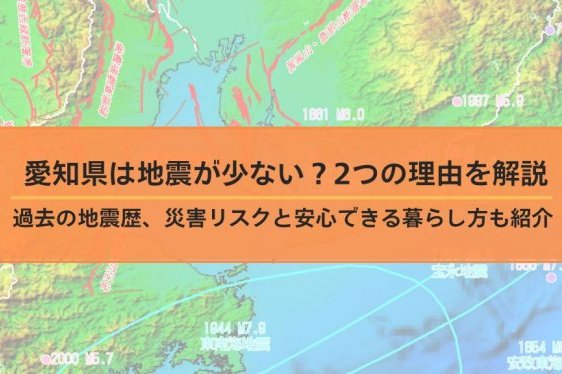
「愛知県は地震が少ない」と言われることがありますが、本当でしょうか? 愛知県は、全国的に見ても地震の発生頻度が少ないとされる地域の一つです。 本記事では、愛知県は地震が少ないと言われる理由を「過去の地震の少なさ・活断層の分布の仕方」といった観点から解説します。 ただし、「地震が少ない=安全」とは限りません。南海トラフ地震のリスクや津波への備えも必要となります。 後半では、愛知県で安心して暮らすための防災対策や、地震に強い家づくりの方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 愛知県は地震が少ない?過去の地震の発生状況を確認 愛知県は、過去の統計データから見ても、全国の中では地震の発生頻度が比較的少ない地域とされています。 たとえば、愛知県および近隣の地域での地震の発生回数を確認すると、三重県や滋賀県とともに、静岡県や岐阜県と比べると地震の発生回数が少ないことが分かります。 過去10年、震度1以上を観測した回数 三重県:191地震 滋賀県:195地震 愛知県:263地震 静岡県:760地震 岐阜県:932地震 ▶参考:気象庁 震度データベース検索 ただし、完全に安全というわけではなく、過去には濃尾地震(1891年)など被害の大きい地震も発生しています。 地震のリスクを正しく理解するためには、実際に観測された回数や被害の記録を知ることが重要です。 愛知県が「地震が少ない」と言われる理由 「愛知県は地震が少ない」と言われる背景には、実際の観測データや地形的な特性があります。 具体的な根拠について「発生頻度・活断層の分布」の2つの視点から紹介します。 過去の地震発生頻度が低い 愛知県は、地震の観測回数が全国の中でも比較的少ない県のひとつです。 物が倒れるなど、一定の被害を引き起こす震度4以上の地震の回数を確認すると、過去10年間で全国で754回の地震が発生している一方で、愛知県では5回しか発生していません。 また、明治以降の大規模地震でも震源が県内であった例は少なく、都市直下型のような直接的な被害を受けたケースも限定的です。 こうした過去の記録から、「愛知県は地震が少ない」と言われることが多くなっています。 活断層が少ない地域もある ▶引用:地震調査研究推進本部 愛知県の地震活動の特徴 愛知県には活断層が点在しているものの、都市部など確認されている活断層の密度が低い地域もあります。 特に名古屋市西部の平野部では大きな活断層が確認されている例が少なく、地震リスクが相対的に低いと評価されることがあります。 もちろん、知多半島から三河山地などにかけては活断層も確認されていますが、全国的に見ると「確認された活断層が密集していない」エリアが多いことが、「揺れにくい」「地震が少ない」と評価される理由のひとつです。 地震が少ない=安全ではない・油断できない理由 「地震が少ない」とされる愛知県ですが、本当に安心してもよいのでしょうか。 南海トラフ地震のような大規模災害が想定される中、過去に被害が少なかった地域でも、今後も同様に地震による被害を受けないとは限りません。 地震発生の頻度だけで、安全性を判断してもよいのか、改めて考えてみましょう。 海溝型地震(南海トラフ地震など)による被災の可能性 ▶引用:愛知県 南海トラフ地震の震度分布 注意する必要があることは、将来発生が予測されている南海トラフ地震の存在です。 南海トラフ地震は100〜150年周期で繰り返される巨大地震で、愛知県も想定震源域に含まれています。 過去の発生時には、紀伊半島や四国南部だけでなく、愛知県沿岸部でも津波や地震の影響による被害が記録されています。 地震の発生頻度が低くても、ひとたび巨大地震が起これば甚大な被害が発生する可能性があり、決して油断はできません。 ▶関連コラム:南海トラフ地震が起こるとどこが危ないのか|県やエリア・対策も解説 過去の大地震による被害も確認 愛知県は比較的地震が少ない地域とされていますが、以下のとおり過去には大きな地震被害を受けた例もあります。 濃尾地震:愛知県での死者数 2,339人 東南海地震:愛知県での死者数 435人 三河地震:愛知県での死者数 2,306人 など ▶参考:名古屋地方気象台 地震災害の記録 たとえば、1891年の濃尾地震(マグニチュード8.0)は、震源は岐阜県内ですが、愛知県西部でも家屋倒壊や死者が出るなど甚大な被害を受けました。 また、1944年の東南海地震では、名古屋市や知多半島で建物被害、津波被害が記録されています。 このように、地震の発生源が県外でも広範囲に被害が及ぶことがありますので、ここ数十年大きな地震に遭遇していなくても油断は禁物です。 過去に被害が小さかった地域でも油断禁物 「これまで被害が少なかったから、これからも安心」という考えは危険です。 地震の被害は地盤や建物の状況、震源との位置関係などにより変化します。 たとえ前回の地震で被害が小さかった地域でも、次の地震では大きな揺れに見舞われる可能性があります。 また、現時点で活断層が確認されていない地域でも、未発見の“隠れた活断層”が存在する可能性もあり、過去の被害実績だけを根拠に安心するのは危険です。 愛知県の地震、津波リスクと安心できる暮らし方 地震の発生頻度が少ないとされる愛知県ですが、南海トラフ地震や津波などへの備えは不可欠です。 地震リスクを踏まえた安心できる暮らし方や具体的な備えについて紹介します。 愛知県の地震リスクを再確認 愛知県は、南海トラフ地震では震度6弱〜7の揺れが予測される地域もあることから安心はできません。 ▶参考:愛知県 津波災害警戒区域の指定について 特に沿岸部では最大20メートル前後の津波浸水も想定され、また液状化の発生リスクも指摘されています。 居住地のハザードマップや地盤情報を確認し、地域ごとのリスクに応じた備えを行いましょう。 津波の想定被災範囲に居住する場合でも、基礎と建物本体が一体化し津波や洪水に耐える鉄筋コンクリート住宅や、屋上部分がシェルターになった住まいも対策として考えられます。 ▶関連コラム:個人でできる南海トラフ巨大地震対策7選│地震の概要や家の安全性を高める方法もご紹介 ▶百年住宅の「流出を防ぐWPC住宅・津波シェルター」 地震に強い(損傷しない)家づくりをする 地震から命と財産を守るには、地震に強い(損傷しない)家づくりが不可欠です。 耐震等級3を満たす構造、正方形などシンプルな形状、鉄筋コンクリート造による強固な構造体など、地震によって倒壊しないことは当然のこととして、揺れによる損傷を受けない住まいづくりがおすすめです。 建物に生じる損傷は余震など、複数回発生する揺れによって蓄積し強度低下を招く可能性があるからです。 また、過去の大地震でも倒壊や損傷が発生していない「実績のある住宅会社」へ依頼することも、安心の家づくりに欠かせないポイントです。 ▶関連コラム:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介 ▶大地震でも安心「無傷の住まい」が分かるカタログ4点セットはコチラ 加えて、地域の地盤特性やハザードマップに基づいた設計も重要です。 液状化のリスクが高いエリアでは基礎構造を工夫したり、避難経路を考慮した間取りを取り入れるなど、立地に応じた設計が求められます。 建物単体の性能だけでなく、地盤や将来の災害リスクを見据えたプランニングが、安全な暮らしの土台となります。 ▶入念な地盤調査・補強で安心の百年住宅の家 被災時の行動を事前にシミュレーションする 万が一の地震に備え、避難ルートや家族との連絡手段、非常用持ち出し袋の準備を日常的に確認、シミュレーションしておくことも重要です。 特に南海トラフ地震では数分で津波が到達する可能性もあり、迅速な初動が重要です。 また、ハザードマップで避難所や浸水区域を確認し、家庭ごとの行動計画を立てておくことが安心につながります。 そのほかにも、次のような備えを家族で共有、実践しておきましょう。 自宅から最寄りの避難所までの安全なルートを歩いて確認 家族が別々の場所にいるときの集合場所と連絡方法の取り決め 非常用持ち出し袋(3日分の水、食料、充電器など)の設置と定期点検 避難先での過ごし方や支援情報の収集手段(行政アプリや防災手帳など) 夜間、停電時のライトや電池、防寒具の備え こうした日常の備えが、いざというときの冷静な行動につながります。 被災後の経済的な打撃に備える 地震によって住宅が損壊、浸水するなどの被害を受けた場合、経済的な負担が発生します。 このため、地震保険への加入、被災後の生活再建に備えた貯蓄やローンの見直しといった経済的な負担を軽減する対策も重要です。 公的支援制度(被災者生活再建支援金など)や自治体の独自支援策を事前に確認し、いざというときに慌てず対応できるよう備えておきましょう。 加えて、そもそも地震や津波によって自宅が被害を受けないようにすることが最も重要な手段といえます。 ▶百年住宅のWPC住宅は過去の大地震でも「無傷」 まとめ|愛知県での地震に強い家は百年住宅へ 「愛知県は地震が少ない」と言われる背景には、過去の発生頻度の低さや確認されている活断層の少なさがあります。 しかし、南海トラフ地震の想定被害や津波リスクを考えると、地震が少なかったからといって安心は禁物です。 地域ごとの今後のリスクを正しく理解し備えを講じることが、安心できる暮らしにつながります。 特に住宅の耐震性は命と財産を守る重要な要素で、信頼できる施工会社を見つけ相談することが防災の第一歩です。 百年住宅では、過去の大地震でも被害ゼロの実績を持つ住宅づくりを行っています。 愛知県で「地震に強い家」を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現
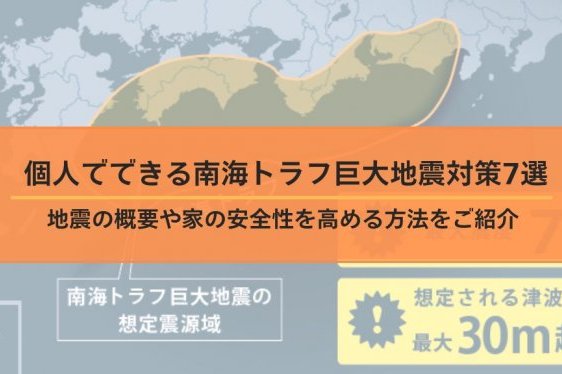
「南海トラフ地震に対して、個人でできる対策はありますか?」 こうした質問を頂くことがあります。 本記事では、南海トラフ巨大地震の概要や被害想定を解説しながら、なぜ個人の備えが重要なのかをわかりやすくご紹介、さらに家庭でできる具体的な対策や、住まいの安全性を高めるための方法も詳しく解説します。 ▶関連コラム:南海トラフ地震が起こるとどこが危ないのか|県やエリア・対策も解説 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現 南海トラフ巨大地震とは? 南海トラフ巨大地震とは、静岡沖から九州沖にかけて広がる「南海トラフ」で発生が懸念されている巨大地震を指します。 マグニチュード8〜9クラスの地震が連動して発生し、広範囲にわたる甚大な被害が想定されています。 被害想定と発生確率 具体的に、政府の地震調査研究推進本部による主な被災想定は次のとおりです。 震度想定:太平洋側の広範囲で震度6強〜7の揺れ(例:静岡・高知・和歌山など) 津波想定:最大34mの津波が沿岸部を襲う可能性(例:高知・宮崎・静岡など) インフラの停止:電気・ガス・水道・通信が1週間以上停止する地域も想定 また、今後30年以内に発生する確率は20~50%、または60~90%程度(予測モデルにより2種類の確率を公表)と想定されています。 ▶地震調査研究推進本部 南海トラフで発生する地震 「個人の対策」が重要な理由 南海トラフ地震に備え、国や自治体もハード・ソフトの両面で対策を進めています。 避難所の整備や津波警報の強化、津波避難タワーの建築などがその一例です。 しかし、住宅の耐震性確保や家庭内の備蓄、安否確認体制など、暮らしに直結する部分までは行政の手は届きません。 だからこそ、最終的には個人単位の備えが命を守る鍵となるのです。 個人、家庭でできる南海トラフ巨大地震対策 具体的に、個人やご家庭でできる南海トラフ巨大地震への対策をご紹介します。 日常生活の中で備えられることから始めて、いざというときに自分と家族を守る行動がとれるようにしておくことが重要です。 建物の耐震性の強化 二次災害(津波、火災など)への対策 家具の固定や避難経路の確保 ハザードマップによる危険、避難場所の確認 食料品や日用品の備蓄 家族との連絡体制の確保 建物の耐震性の強化 南海トラフ地震のような巨大地震では、建物の倒壊が命に直結します。 自宅が安全でなければ、備蓄や避難の準備も十分に活かせません。 このため、住まい自体の「耐震性を強化すること」が何よりも重要です。 具体的には、次のような対策が有効です。 耐震等級2または3の建物を選ぶ 古い住宅には耐震診断を実施し、必要に応じて補強する 屋根を軽量素材に変える 柱や壁の配置をバランスよく設計する 開口部(窓・玄関)を増やしすぎない これから家を建てるなら、過去の大地震でも倒壊、損傷ゼロの実績を持つ住宅会社を選ぶことも大切です。 ▶関連コラム:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介 ▶大地震でも安心「無傷の住まい」が分かるカタログ4点セットはコチラ 二次災害(津波、火災など)への対策 地震そのものの揺れに加えて、揺れに伴って発生する二次災害への対策も重要です。 特に南海トラフ地震では、その影響が広範囲に及ぶと想定されています。 たとえば、代表的な二次災害として次のようなものが挙げられます。 津波による浸水、流失 通電再開による火災(通電火災) ガス漏れによる爆発・出火 液状化現象による建物の傾き このような二次災害による被害を防ぐためには、鉄筋コンクリート造など耐震性のある住宅や高基礎の構築、感震ブレーカーの設置、高台への避難経路確保など、建物への備えと迅速な避難動線の両面から対策を講じることが大切です。 ▶耐震性、耐火性が高く、津波にも対応する「シェルター付き」百年住宅の住まい 家具の固定や避難経路の確保 大地震では家具の転倒や移動によって、けがをしたり避難経路がふさがれたりするリスクがあります。 特に夜間や停電時には視界も悪く、思わぬ事故につながる可能性があります。 タンスや冷蔵庫、テレビなどの大型家具や家電は、壁にしっかり固定し、就寝場所や通路にはできるだけ配置しない工夫が必要です。 また、ドア付近や廊下などは物を置かず、スムーズに避難できる空間を確保しておきましょう。 ▶関連コラム:南海トラフ地震発生時どこに逃げる?避難行動の想定や事前の対策も紹介 ハザードマップによる危険、避難場所の確認 地震や津波、土砂災害などによる被災リスクを事前に把握するには、自治体が公開しているハザードマップの確認が不可欠です。 自宅が浸水想定区域にあるか、近隣に避難所があるか、避難経路は安全か、といった点を家族で一度確認しておきましょう。 紙に印刷しておけば、停電や通信障害時にも安心です。 また、これから家を建てる方は、ハザードマップをもとに土地の安全性を見極めることで、災害リスクを軽減した住まいづくりにもつながげられます。 ▶屋上に設置する津波避難シェルター 食料品や日用品の備蓄 大規模地震の発生後は、ライフラインや物流の停止により、食料や日用品の入手が困難になることが想定されます。 政府は最低3日分、可能であれば7日分以上の備蓄を推奨しています。 飲料水、長期保存食、トイレ用品、衛生用品、乾電池、常備薬など、家族構成に応じた備えが必要です。 備蓄の内容は定期的に見直し、消費と補充を繰り返す「ローリングストック」も有効です。 ▶︎備蓄品を適切に消費する「ローリングストック」 家族との連絡体制の確保 大地震の発生時には、家族が離れた場所にいる可能性が高く、連絡手段の確保が重要になります。 通信障害が発生することも想定し、以下のとおり複数の手段やルールを事前に決めておきましょう。 災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を共有 災害用伝言板サービス(各キャリア)を活用 SNSや安否確認アプリを事前にインストール 集合場所や避難所を「◯◯に集合」と明確に決定 安否確認の順序(祖父母▶子▶親 など)も共有 最も重要な「住まいの安全性」を高めるために 命を守るために最も大切なものは「住まいそのものの安全性」です。 どれだけ備蓄や避難準備を整えても、家が倒壊してしまっては意味がありません。 では、どのように検討すれば、安全性が高い住まいになるのか、大切な考え方をお伝えします。 耐震等級で表されない耐震性を意識する 耐震等級は住宅の耐震性能を数値で示す指標ですが、耐震等級だけでは住宅の「真の強さ」を測ることはできません。 以下の要素のように設計や施工の精度、実績のある住宅会社の選定も含めて、等級では測ることのできない耐震性に関する要素を確認することが重要です。 設計、施工の精度 柱や壁の配置バランス(直下率) 建物の形状(シンプルな形が有利) 基礎の強度や鉄筋の量 共振現象を回避する設計 など ▶地震時の被害が拡大する原因のひとつ「共振現象」、対策済みの百年住宅の家 建物に加えて地盤の十分な強度も確保する どんなに耐震性の高い建物でも、軟弱な地盤の上では揺れが増幅され、倒壊の危険性が高まります。 家づくりの際は、必ず地盤調査を実施し、その結果に応じた基礎設計や地盤補強を行うことが大切です。 液状化のリスクがある地域や埋め立て地、傾斜地では特に注意が必要です。 百年住宅では、SWS試験に加えて精度の高いボーリング調査も導入、必要に応じて柱状改良などの基礎補強を実施しています。 強い家は、強い地盤とセットで成立することを認識しましょう。 ▶入念な地盤調査・補強で安心の百年住宅の家 過去の地震でどのような被害を受けたのか確認する 住宅の性能を知るうえで有効なのは、過去の地震で実際にどのような被害があったのかを確認することです。 たとえば阪神・淡路大震災や熊本地震では、構造の違いによって被害の大きさに差が出ました。 軽量鉄骨造や木造の中には全壊した例も多くある一方で、壁式構造の鉄筋コンクリート住宅では“無傷”の実績を残した事例もあります。 建築基準法を満たすだけでは不十分な場合もありますので、実際の被害データに基づいた判断が、将来の命と財産を守るカギになります。 ▶関連コラム:【鉄筋コンクリートの家】8つのメリット、5つのデメリット│後悔する瞬間と対策も解説 まとめ|南海トラフへの備えは百年住宅へ ▶30畳の大空間LDKと富士山が見える屋上ジャグジーのある家【沼津市】 南海トラフ地震は、いつ起きてもおかしくないとされる巨大災害です。 備蓄や避難準備も重要ですが、最も大切なことは「倒壊しない、損傷しない家」に住むことです。 いざというとき、家族の命を守る“最後の砦”になる、強固な家を建てて南海トラフ巨大地震に備えましょう。 百年住宅は、阪神・淡路大震災をはじめ、数々の大地震を“無傷”で乗り越えてきた鉄筋コンクリート住宅を提供しています。 耐震・耐火・耐久性に優れた構造で、災害が多く発生する時代も安心して暮らせる住まいを実現しましょう。 ▶大地震でも無傷の家を「百年住宅」で実現